GACKTさんが語る「週刊誌報道のあり方」──真実とは何か、私たちが考えるべきこと

2025年5月19日、ミュージシャンのGACKTさんが、自身の公式SNS「X(旧Twitter)」を通じて、週刊誌報道に対するご自身の考えをあらためて発信されました。これまでも何度か週刊誌の在り方に疑問を呈してきたGACKTさんですが、今回の投稿では、より一層踏み込んだ見解を示され、多くの反響を呼んでいます。
「週刊誌はビジネスである」──表面上の正義と実際の目的
GACKTさんはまず、週刊誌の報道姿勢に対する根本的な問題として、「週刊誌とは本質的にビジネスであり、利益を追求する存在である」という点を強調されています。
「週刊誌はあくまでビジネスです。表向きには“公平性”や“中立性”を掲げてはいるものの、実際のところ彼らが最も重視しているのは、『面白い』『読まれる』『売れる』という3つの要素です。そうでなければ収益には繋がりませんから」
というように、週刊誌が正義の味方のように振る舞いながらも、読者の関心を引くことが最優先であるという点を鋭く指摘されました。
意図的な印象操作──“真実っぽさ”があれば十分?
さらにGACKTさんは、ある架空の例を使い、週刊誌がどのように印象を操作しているかについて説明されています。
「たとえば、有名人のMさんと一般人のAさんという登場人物がいた場合、Mさんを“加害者”として描いた方が読者の感情を刺激でき、記事として注目されやすくなります。たとえAさん側にも過ちがあったとしても、『どっちもどっち』という記事では売れないため、そのような視点は排除されてしまうのです」
このような手法をGACKTさんは“意図的な印象操作”と呼び、真実を伝えることよりも、「真実っぽく見える内容」にすることが優先されているのではないかと警鐘を鳴らしています。
「週刊誌側が事実を正確に把握できるわけがありません。彼らにとって重要なのは、事実かどうかよりも、“それっぽく”見えること。そうすることで記事が拡散され、結果として広告収入が得られる。つまり、それが彼らにとっての“成功”なのです」
“点在する真実”による印象操作のテクニック
GACKTさんはさらに、「すべてが嘘だとは言わない」としながらも、「むしろ、一部の真実を意図的に盛り込むことで、全体を“本当のこと”のように見せかけるのが、週刊誌の売れるための戦略なのではないか」と語られました。
「これは一種の印象操作のテクニックと言えるでしょう。その情報とメディアを“脅し”のように使い、人々の行動に影響を与えることすらあります。それを“抑止力”と呼ぶのは、耳を疑いたくなるような話です」
このように、GACKTさんはメディアが持つ“情報の力”に対する警戒心と、それを安易に“社会の抑止力”と見なすことへの疑問を強く表明されました。
情報を受け取る側にも責任がある
GACKTさんの投稿は、発信者側に対する批判だけにとどまりませんでした。むしろ、「情報を受け取る側」にも問題があるのではないかと、読む側の姿勢についても問いかけています。
「世の中には、ネガティブな情報を好み、それをストレス発散の手段にしたり、会話のネタとして消費する人々が少なからず存在します。週刊誌に書かれていることをそのまま信じ、面白がって盛り上がっているような状況も見受けられます。これは、受け取る側にも一定の責任があると言わざるを得ません」
そしてGACKTさんは、こうした風潮を「滑稽」と表現し、私たち一人ひとりに対して次のように呼びかけました。
「どんな情報が出ようとも、それが本当かどうかを知ることができるのは、当事者だけです。憶測で人を攻撃したり、興味本位で盛り上がったりするのは、とても愚かな行為です。それよりも、もっと楽しいことに目を向けて、自分の人生を前向きに生きるべきではないでしょうか」
共感の声が相次ぐ投稿に
このGACKTさんの投稿には、多くの共感の声が寄せられています。「その通りだと思う」「一つひとつの言葉が心に刺さった」「考えさせられました」など、X上では反響が広がっており、日頃何気なく目にしているメディア情報を、いま一度見つめ直すきっかけとなっています。
まとめ
GACKTさんが発信された今回のメッセージは、私たちが日々触れている情報の受け取り方や、メディアに対する姿勢を見直す重要な機会を与えてくれました。情報社会の中で生きる現代人として、何を信じ、どう向き合うかを自分で考える力が求められています。
GACKTさんのように、メディアの裏側を冷静に捉えた発信は、これからの時代においてますます重要になってくるのではないでしょうか。真実とは何か、私たちは何を基準に信じているのか──そんな問いを持ちながら、日々の情報と接していきたいものです。


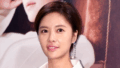
コメント